スマホの情報、本の情報──なにがどう違うのか、全部まとめてみた
今の時代、情報はあふれてる。でも、その情報、本当に“残って”る?
そもそも情報多すぎ問題
現代は、まるで情報の海に生きているようなもの。
スマホを開けば、SNSやニュース、メール、アプリ…
一日中、絶え間なく新しい情報が流れ込んでくるし。
けど、ふとした瞬間に思いませんか?
「え、さっきまで何見てたんだっけ?」「なんでこれに1時間も使ってたの…?」
情報過多の時代にあって、私たちはどう情報を選び、どう記憶していくのか。
その中で、スマホと本、この二つのメディアがどんな役割を果たすのかを考えてみたいと思います。
スマホ、本、それぞれの情報の性質
もういきなり、比較表作っちゃいました!
| 項目 | スマホの情報 | 本の情報 |
|---|---|---|
| スピード | 超高速、リアルタイム | 遅い、熟成 |
| 密度 | 薄い・断片的 | 濃い・一貫性 |
| 定着性 | 忘れやすい | 残りやすい |
| 精度 | バラバラ、アルゴリズムに左右される | 編集・検証あり |
| 構造 | ランダム、断片的 | 論理的・体系的 |
| 身体性 | 少ない、軽い | 五感に残る |
| 思考への関与 | 受け身 | 能動的、思考を促す |
| 感情・人生への影響 | 焦り・情報疲れ | 落ち着き・没入・気づき |
情報のスピード
圧倒的にスマホが早い!!リニアモーターカーどころではない。
それで言うと本は亀。ウサギとカメみたいな展開になるはずもなく・・・
ニュースや金融、新技術、エンタメ、天気予報、スポーツに災害情報。
早さが求められる分野はスマホに任せたらいい!
情報の密度
スマホの情報、サラッとしてる。
「見た気がするけど、内容までは覚えてない」現象、日常茶飯事。
一方で、本は1ページに込められた思考の深さが圧倒的。
同じ文字数でも、刺さる密度がまるで違う。
それにしても、内容ゼロの謎ショート動画に吸い込まれてくあの感覚、なんなんだろうね…笑
情報の構造
スマホの情報は、バラバラに飛んでくる断片。
関連性も順番もバグってる。
でも本は、導入から本論、結論へと流れがある。
物語でも論文でも、情報が積み上がっていく心地よさがある。
“知識が階層化されていく感覚”、これが本の魅力。
スマホは無人駅、本は東京駅、そのくらい構造差がある。
情報への関与
スマホは受動的、本は能動的。
スマホって実際調べようと思ったことは2、3分で見終わって、その後調べる予定もなかった情報で2、3時間使ってるのなんで?笑
本はむしろ本気出さないと2、3時間も向き合っていられないのに・・・
見始めるのも、スマホは一瞬なのに、本だと「見よう、見よう」で気づけば深夜。
これ乗り越えて本を読んでる時点で、そりゃ定着度違うやろってこと!?
まぁリアルに“流し見”と“ちゃんと読もうとして見る”の違い、でかいんですよね。
結論:引き分け
(本を優遇してるように見えたかも知れないけど、)今回の勝負は引き分け。
スマホの便利さ、スピード感、情報量は流石にヤバい!普通に最強でしょ!
とはいえ、本の凄まじさも余裕でスマホに匹敵すると感じてもらえたらなぁと。
本でじっくり考え、スマホで瞬時に情報をキャッチする。
このバランスを取ることで、より深い理解と有益な情報を得ることができるのかもしれない。
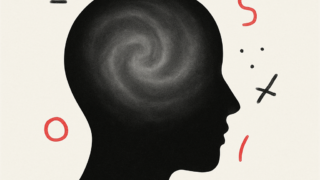

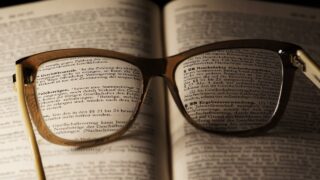




コメント